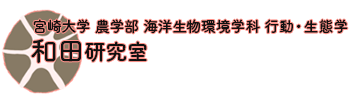プロローグ~まず、どうやって研究を始めるの?~
私の場合は,まず,海岸に出てゆっくり磯観察をすることから始めます。焦ることなく,とにかくゆっくりと生物と会話をする気持ちでぼーっと周りを見渡します。気になることがあればすべて野帳にメモ!〇〇の色が本州と違う?〇〇は個体数が多いので研究しやすそう。〇〇の下にいつも××がいる・・・。いったん持ち帰り,その中で,作業仮説を立てます。そして,その仮説は検証できそうか,先行研究のどこに位置づけられるか?理論仮説は何になるか(論文を書く時のイントロの1文目は何になるか)?自分が主体性をもって,モチベーションを保って遂行できるほど興味の持てる課題か考えます。方法として,操作実験を用いることが多いです。また,一貫して,野外での検証を大事にしてきました(野外実験が大好きです)。ただ,子供が生まれてからは,室内実験や室内観察をベースとした研究も増えています。
1)捕食者が被食者を介し、海藻群集を改変する
キーワード①:直接・間接効果(間接相互作用)
生態系において,ある生物種は他種と関係し合って生きています。これを”種間相互作用”と言います。また,そこには直接的な関係(直接的な相互作用)と,間接的な関係(間接相互作用)があります。直接的に関係がなく,一見何も関係のない種どうしも,目には見えない影響を間接的に及ぼして(及ぼし合って)います。例えば,捕食者-被食者-海藻の関係を知りたい時,捕食者が被食者の個体数をどれだけ減らしているか,被食者は海藻をどれくらい食べてその量を減らしているか,この直接的な関係だけを考えていても,実際の生物の量の変動を完全には説明できないでしょう。その大きな一因として,捕食者が被食者を介して海藻に及ぼす間接的な影響を考慮できていないという点が挙げられます。捕食者が被食者を減らすことで,海藻は間接的な正の影響を受け,増えることができるかもしれません。間接効果を正しく評価することは,多くの生物が共存する生態系の構造や動態を明らかにする上で非常に重要です。

キーワード②:肉食性の貝と藻食性の貝
貝の中には,海藻を食べる藻食性の貝と,他の貝などの動物を食べてしまう肉食性の貝がいます。あの,のろのろとしているイメージの貝が,どうやって他の動物を食べているのでしょうか?肉食性の巻貝が藻食性の笠貝を食べる例を考えてみましょう。肉食性巻貝が藻食性笠貝を見つけると,その殻の上に乗ります。そして,口吻(長い口)を延ばし,先っぽ(穿孔盤)から酸を出します。すると,貝殻が溶けていきます。これだけではまだ穴が開きません,次に使うのは歯舌(歯)です。やわらかくなった貝殻を歯でガジガジ削るのです。とかして削ることを繰り返し,最後に口の部分から中身をじゅるっと食べてしまいます。食べられた貝の貝殻には丸い穴が開いています。海岸などに行って貝殻を集めることがあれば,是非丸い穴を探してみてください。

キーワード③:直接殺す vs 恐怖を与える
捕食者はその名の通り,被食者を”捕食”し,その数や量を減らします。このように,捕食者が被食者を食べ,その密度を変えることは,「Consumptive Effect 消費型効果」,それを介して生産者に与える影響は,「Density-Mediated Indirect Interaction 密度媒介型間接相互作用」 と呼ばれています。しかし,被食者側もただ食べられることを待っているだけではありません。捕食者の存在を察知すると,その形質(行動や形態、生活史など)を変え,食べられないようにしようとします。捕食者が被食者の形質を変えることを,「Non-Consumptive Effect 非消費型効果」,それを介して生産者に与える影響を「Trait-Mediated Indirect Interaction 形質媒介型間接相互作用」と呼びます。非消費型効果やそれによる形質媒介型間接相互作用は,被食者が死なずとも,例えば捕食者の匂いなどにより引き起こされます。そのため,この効果は迅速,かつ1個体のみでなく広範囲に,時にはその生物の生涯にわたり,また次世代へと長期的に及ぶと考えられています。「Ecology of Fear 恐怖の生態学」という言葉も生まれ,様々な分類群において,捕食される恐怖がもたらす影響が調べられています。

[1] 捕食者は被食者の密度・形質の変化を引き起こし,海藻の群集構造を変える
Wada et al. 2013 (Ecology)
岩礁潮間帯に生息する,笠貝のキクノハナガイ Siphonaria sirius (以後笠貝) は,家痕(かこん)という家のようなものを持っていて,餌を食べに家を離れても,必ず家に帰ってくる,”帰家行動”を示します。その家の周りには褐藻 Ralfsia sp.が,さらにその周りに緑藻 Ulva sp.が生えていますが,笠貝は緑藻を好んで摂餌します。ここから笠貝を除去すると,褐藻が生えられなくなり,あたりは緑藻だらけになってしまいます。では,ここに,笠貝の捕食者である巻貝のイボニシThais clavigera (以後巻貝)が加わるとどのようなことが起こるでしょうか。潮間帯に点在する大型の転石24個を実験区とし,被食者笠貝を徐々に除去する「密度」処理と,笠貝が巻貝に捕食された匂いが小ケージ内から放出される「形質」処理を組み合わせ,4つの処理群を作成しました。実験は夏季の1か月間行いました。その結果,自然の捕食圧下では,捕食者の匂いがすると被食者が家にこもり,緑藻を食べに行かないこと,その結果,捕食による密度媒介型と,匂いによる形質媒介型の両間接効果が同程度の強さで引き起こされ,藻類相が褐藻から緑藻へとダイナミックに変化することが分かりました。褐藻は,笠貝がいなくなってしまう,もしくは緑藻を食べれなくなると,そこに生え続けることができなくなってしまうようです。

[2] お腹がすくと捕食者への反応が鈍る
Wada et al. 2015 (JEMBE)
巻貝がいると笠貝は家にこもって餌を食べなくなってしまう。このままいくと笠貝は死んでしまうのでしょうか?そんなことはなくて,笠貝はお腹がすくと,たとえ捕食者の匂いがしていても餌を食べに家から出てくるようです。周りに同種の笠貝があまりいない時(低密度の時),笠貝は餌を十分に食べられているようで,捕食者巻貝がいると,密度や形質の変化を介して間接的に藻類相が褐藻から緑藻に変化しました。一方で,周りに同種がたくさんいる時(高密度の時),笠貝は十分に餌を摂餌できなくなり,匂いがあっても摂餌を止めることはなく,藻類への間接効果も見られませんでした。捕食リスクの生態的なインパクトは,被食者が様々な状況下でどのように摂餌努力を配分するかによって決定するため,被食者の状況を考慮することは間接効果の決定機構において必要不可欠であると考えます。
[3] 捕食者が駆動する間接相互作用は,ダイナミックな季節性によりリセットされる
Wada et al. 2017 (Ecology)
巻貝も笠貝も,夏季に非常に活発に活動します。では,その他の季節では,捕食者は被食者に,そして藻類相にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。大型の転石54個を実験区とし,これまでと同様の実験を長期間(約9か月間)行いました。その結果,巻貝の捕食圧は夏季に非常に高く,15%程度の笠貝を捕食してしまうことが分かりました。この笠貝の密度変化を介して,藻類相が変化しますが,その影響は2か月程度しか続きません。一方で,巻貝の存在であまり緑藻を食べなくなる,という笠貝の形質の変化により,藻類相が変化し,かつ,その影響は密度を媒介する効果よりも3カ月近く長続きしました。しかし,両方の間接効果(密度媒介型と形質媒介型)が生じても,春になると褐藻が生え,実験をする前と同じような藻類相になりました。つまり,藻類相は間接効果により変動しますが,一年のうちに元に戻ること(間接効果のリセット)が明らかになりました。そしてこの機構には,冬に低くなる捕食圧と,それに伴った笠貝の成長遅延の回復,秋から冬に起こる笠貝の新規加入個体の定着による密度回復という,生態系構成種の季節性が関与していると考えられます。捕食者が駆動する間接効果が藻類相に影響を与えますが,それが回復し,効果がリセットされていく過程は見ものでした。今回対象として系でいう”冬”のように,捕食圧の低い時期の群集の動態に注目することは,生態系の維持機構を考える上でも重要であると考えられます。
2)捕食者が被食者の繁殖特性へ与える影響
[1] キクノハナガイの幼生の発生と孵化
Wada and Yusa 2021 (MR)
笠貝キクノハナガイは,夏7月から9月の小潮時に交尾・産卵をします。卵から幼生が孵化すると,浮遊幼生となって海を漂い,数か月後にまた岩場に定着・成長するという生活史を送ります。一つ一つの卵は卵嚢というカプセルに,そしてその卵嚢は写真のような卵塊に包まれて産まれてきます。本研究では,本種の非常に短い幼生発生の過程を記録しました。受精卵が産卵されると,すぐに分割期に入り,10時間ほどで胞胚期に,14時間ほどで原腸胚期,19時間でトロコフォアに,そして1日半ほどで前期ベリジャー,そこから半日程度で後期ベリジャ―へと発生が進みます。これは他のShiponaroa属と比べても非常に早いということが分かりました。なぜここまで発生が早いのでしょうか?1つは,交尾・産卵というイベントが,暑い夏に起こるという点が挙げられます。温度が高いほど,発生は早まります。しかしこの夏は,卵を食べてしまう腐肉食性の巻貝が非常に活発に活動している季節でもあります。そこで発生が早いもう一つの理由として,卵塊を食べてしまう捕食者の存在を考えました。もしかすると彼らは,卵塊を食べられないよう,発生を早める方向に進化したのかもしれません。

[2] 笠貝の成体の捕食者と卵の捕食者の存在が,幼生の孵化タイミングに与える影響
Wada et al. 2025 (Oecologia)
準備中…
3)粘液ねばねばネットワーク 貝類が塗布する粘液を介した種間相互作用
[1] 捕食者 vs. 被食者 粘液という残る情報を使った双方向の情報戦
Wada et al. (under review)
準備中…