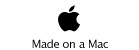細菌ゲノムの多様性がおもしろい
患者や環境から分離される菌株のゲノムを同種(または近縁種)に属する株と比較してみると、いろいろな“ 違い” が見えてきます。例えば、病原細菌が持つ注目すべき病原性関連遺伝子の多くはファージやプラスミド、トランスポゾンといった“ 動く遺伝子” により他の細菌から運ばれてきたことが分かります。また、表層多糖や線毛、鞭毛といった菌体表層に発現する構造体をコードする遺伝子(領域)が株間で非常に多様化していることが分かります。
ゲノムの多様性は、もちろん菌株の表現型と密接に関係しており、さまざまな環境で生きていく為に多様に適応してきた痕跡と言ってもいいでしょう。そんな細菌ゲノムの多様性に注目した研究を行っています。
“ 超” 多様性領域 - O 抗原コード領域 -
LPSの糖鎖部分であるO(オー)抗原(図)は、構成される糖の組み合わせによって異なる抗原性を示し、大腸菌では分かっているだけで180種類以上のO抗原タイプがあります(ちなみに、食中毒細菌として有名な大腸菌O157は「157番目のO抗原タイプ」という意味で使われています)。O抗原タイプの違いは染色体上の10から20個の遺伝子によって構成される「O抗原コード領域」の多様化によるもので、この領域はゲノム全体を見ても特に多様化した領域と言えます。そんな「O抗原」と「O抗原コード領域」に注目した研究を行っています。
1. 大腸菌O抗原合成関連遺伝子のデータベース作成とその利用

2. 稀な血清型(O抗原型/H抗原型)に分類される病原性大腸菌の解析
3. 既存のO抗原型には当てはまらない腸管出血性性大腸菌の解析
4. O抗原の多様性と細菌の環境適応戦略
現在、以下の4つのテーマについての研究を行っています。